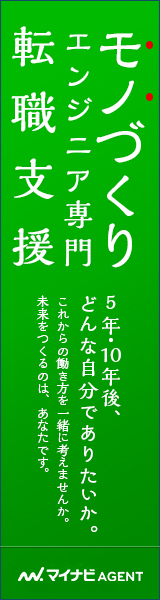次世代データセンターを支える光電融合技術のすべて

1. 光電融合とは?
光電融合(Photonic-Electronic Integration)は、電子回路(エレクトロニクス)と光通信回路(フォトニクス)を1つの半導体チップやパッケージ内に統合する技術です。
これにより、チップ間・サーバー間のデータ転送を光信号で行い、電子信号の限界を突破します。
2. データセンターが直面する課題
データセンターは、クラウドサービスや生成AI、動画配信などの急拡大によって、次の課題に直面しています。
帯域幅不足:AIやビッグデータ処理で1秒間に数TBのデータ転送が必要
消費電力増大:電子信号の配線長や速度が増すほど電力消費が急増
発熱問題:サーバー内の高密度配線で熱が蓄積しやすい
レイテンシ(遅延):遠くのサーバー間通信では遅延が無視できない
電子だけの配線では、この成長スピードに追いつけなくなっています。
3. 光電融合がもたらすブレイクスルー
3-1. 高速化
光は電気よりも長距離でも速度低下がほぼない
AIサーバー間を数百Gbps〜Tbpsクラスで接続可能
3-2. 低消費電力
光通信は長距離伝送でも消費電力が小さい
電子回路の「信号増幅」の回数を削減できる
3-3. 発熱抑制
信号損失が少なく、熱の発生源となる抵抗損失が減る
冷却コスト削減にもつながる
3-4. 小型化
光配線によりケーブル数・配線スペースの削減が可能
ラックあたりのサーバー密度を上げられる
4. 光電融合の仕組み
光電融合チップは、電気信号 ↔ 光信号の変換部(光変調器やフォトダイオード)を内蔵しています。
GPUやCPUが処理したデータを電気信号で生成
チップ内の光変調器で光信号に変換
光ファイバーで別のチップやサーバーへ伝送
受信側で光信号を電気信号に変換し処理
これを半導体パッケージレベルで統合することで、従来の外付け光モジュールよりも低遅延・低コスト化が可能になります。
5. 実用化に向けた技術動向
シリコンフォトニクス
CMOSプロセスで光素子を作る技術。IntelやIBM、TSMCなどが研究開発中。Co-Packaged Optics(CPO)
スイッチASICやGPUと光モジュールを同じパッケージに実装。CiscoやBroadcomが開発。光電融合プロセッサ
NTTが推進するIOWN構想では、光電融合型のデータ処理チップを開発中。
6. データセンターへのインパクト
光電融合が本格採用されると、次のような変化が期待されます。
生成AIクラスタの高速化:数千GPUの並列学習がより効率的に
省電力化:消費電力を最大40〜50%削減(冷却負荷も低減)
規模拡大:ラック間・データセンター間の高速光接続で分散処理性能向上
運用コスト削減:配線・冷却・電力コストの低減
7. 課題と展望
製造コスト:光素子を半導体と一体化する工程が高コスト
標準化の遅れ:インターフェースやプロトコルの統一が必要
発熱の局所集中:光素子周辺の熱設計が課題
しかし、生成AIやメタバース、6G時代に向け、光電融合は次世代データセンターの必須技術になると予測されています。
8. まとめ
光電融合は、データセンターの「通信速度・省電力・小型化」を同時に実現する革命的な技術です。
特に、AIモデルの大規模化やデータトラフィック増加が続く中で、電子だけの通信では限界が近づいており、光の力を取り込むことでその壁を突破できます。
今後5年以内に、光電融合はデータセンターだけでなく、スーパーコンピューターやクラウドAI基盤の標準構成になる可能性が高いでしょう。